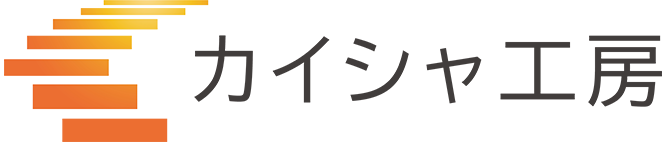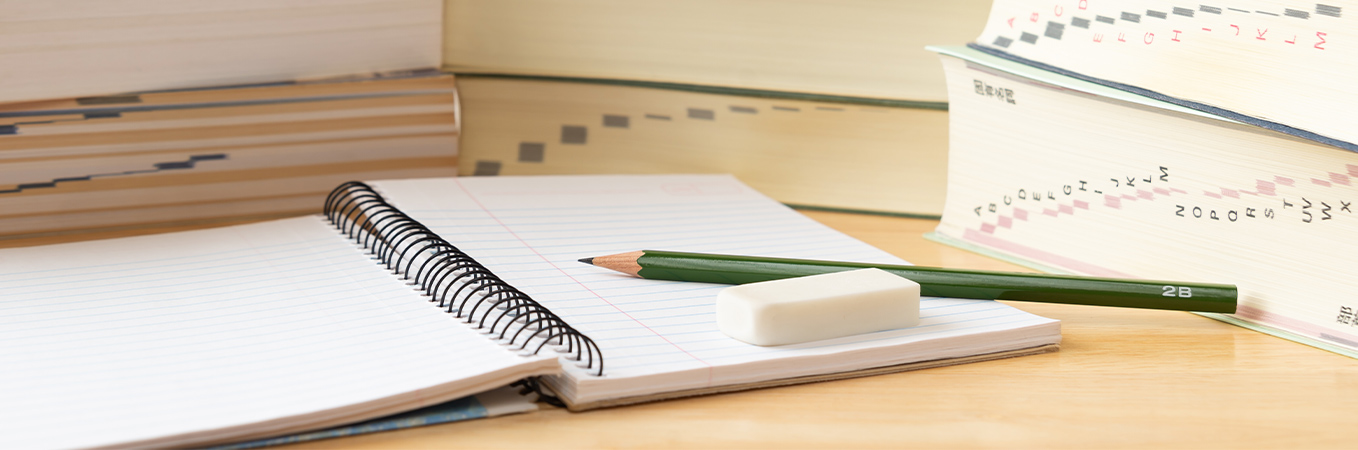日本における大学進学率は近年大きく変化しています。2000年代に入って初めて50%を超え、現在では60%前後となっています。この変化は、学歴の価値や就職市場にどのような影響を与えているのでしょうか。また、大学の進学率が上昇することで、社会にどのような変化が生まれているのかを考えていきます。
大学進学率の変遷と背景
かつて、大学進学は一部の限られた人々のものでした。1970年代から90年代にかけては30〜40%程度の進学率でしたが、バブル崩壊後の1990年代以降、急速に進学率が上昇しました。この背景には、いくつかの社会的要因が関係しています。
- 景気の低迷:バブル崩壊後、日本経済は「失われた10年」と呼ばれる低迷期に突入しました。企業の採用活動が鈍化し、就職難が続く中で、より良い職に就くために大学進学を選択する若者が増えました。
- 大学設置基準の緩和:1990年代後半から2000年代初頭にかけて、政府は大学の設置基準を緩和しました。その結果、新設大学や短期大学の四年制大学化が進み、入学のハードルが下がりました。
- 少子化の影響:人口減少が進む中で、大学は学生を確保するために入試を多様化し、受験競争が緩和されたことで、より多くの人が進学しやすくなりました。
こうした要因が重なり、大学進学は特別なものから「一般的なもの」へと変化しました。
学歴の価値は今後どうなる?
「大学を卒業すると生涯年収が高くなる」とよく言われますが、これは過去のデータをもとにした話です。大学進学率が50%を超えた現在、大卒というだけで高収入が保証されるわけではありません。
大学進学が一般的になると、学歴の価値は変わります。例えば、1970〜90年代の30%程度の大学進学率の時代、大卒は「選ばれた人」でした。しかし、進学率が50%を超えた今では、「当たり前のもの」となり、その希少価値は低下しています。
このような状況下で、今後学歴の価値はどのように変化していくのでしょうか。特に注目すべき点は、以下のような点です。
- 大学卒業=安定ではない時代の到来:かつては「大卒=安定した職業」という図式が成立していましたが、現在はそれが崩れつつあります。実際に、企業の採用基準が学歴重視からスキル重視へと移行している傾向があります。
- 新しいキャリアの形:IT分野やスタートアップ企業では、実績やスキルが評価されることが増え、必ずしも大卒である必要がない職種が増えています。プログラミングやデザインなど、特定の技術を持つ人は独学でスキルを磨き、高収入を得るケースも珍しくありません。
- 大学の価値の多様化:学問的な探究を深める場としての大学の価値は依然として存在しますが、単なる「就職のための資格」としての役割は薄れつつあります。
学歴の持つ3つの意味
学歴が評価される理由には、いくつかの理論があります。
1. 人的資本論
- 大学で高度な教育を受けることで、知識やスキルが向上し、高収入の仕事に就きやすくなるという考え方。
- 例えば、専門的な知識を身につけた理系学部卒業生が技術職に就くケース。
2. シグナリング理論
- 難関大学合格は、知的能力や努力の証明となり、採用時に有利に働くという考え方。
- たとえ実務経験がなくても、「この大学に入学できた=優秀」というシグナルを企業が受け取る。
3. 社会的閉鎖理論
- 学歴を持つ人々が、同じ学歴を持つ人を優遇することで、学歴の価値が維持されるという考え方。
- 例えば、特定の大学のOB・OGネットワークが強い企業では、その大学の出身者が優遇される傾向がある。
これからの大学進学の意味
現在、日本の大学進学率は高水準を維持していますが、少子化の進行により、一部の大学は生き残りをかけた戦略を模索しています。今後は、
- 大学の淘汰が進む:定員割れする大学が増え、一部は閉校の可能性も。
- 多様な入試方式の増加:学力試験だけでなく、総合型選抜などの入試方法が一般化。
- 学歴以外のスキルの重視:大学卒業の有無よりも、実務経験やスキルを重視する企業が増加。
今後は「大学に行くこと自体が価値を持つ」時代ではなく、「何を学び、どう活かすか」が重要になってくるでしょう。進学を考える際には、「大学を卒業すること」だけでなく、「大学で得られるスキルや経験」が将来のキャリアにどのように役立つのかをしっかりと見極めることが必要です。
まとめ
大学進学率の上昇に伴い、学歴の価値は変化しています。大卒であることが以前ほどの希少価値を持たなくなった今、進学の意味を改めて考えることが重要です。「どの大学に行くか」よりも「大学で何を学び、どう活かすか」に焦点を当てたキャリア設計が求められる時代になっています。
また、進学の選択肢だけでなく、専門スキルの取得や実務経験を積む方法も視野に入れることで、より柔軟なキャリアを築くことが可能となるでしょう。
もっと詳しく知りたい方へ
今回の内容は、Podcast番組をもとにまとめました。より詳しい対話形式での解説を聞きたい方は、ぜひPodcastをチェックしてみてください!
📢 Podcastの詳細はこちら