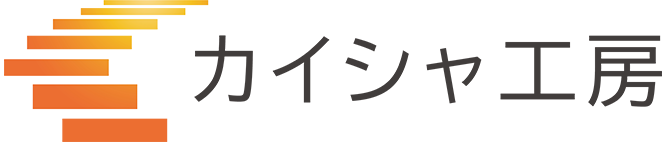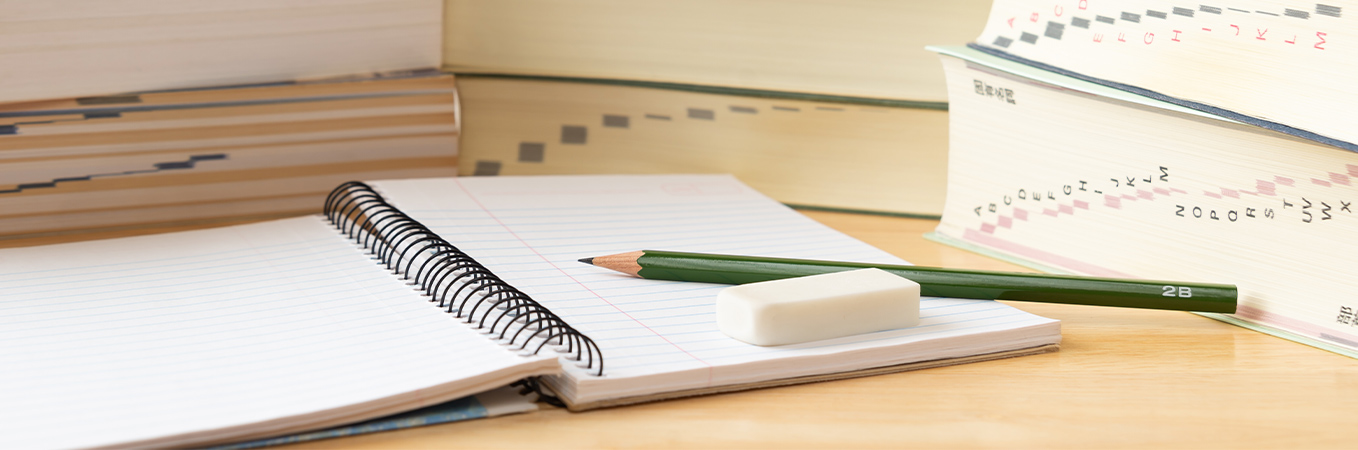戦後から現在にかけて、日本の教育と働き方は大きく変化してきました。その中で、「職業のための教育」が次第に影をひそめ、「学歴がすべて」という考え方が強まっていきます。この記事では、日本特有の雇用の仕組みと、それが教育や社会に与えた影響についてわかりやすく解説します。
高度経済成長期に生まれた日本的雇用とは?
1960〜70年代の高度経済成長期、日本では働く人が足りない状況が続いていました。そのため、企業は長く働き続けてもらえるように、独自の雇用ルールを作りました。
日本的雇用の主な特徴
- 終身雇用:一度入社すれば、定年まで同じ会社で働くのが当たり前
- 年功序列:働いた年数が長いほど給料や役職が上がる
- 新卒一括採用:学生を毎年一斉に採用して、一から育てる
- 企業内教育:必要な知識やスキルは入社後に会社で教える
- 定期異動:いろんな部署を経験させて、会社のことを広く理解させる
- 職能給制度:どんな仕事をしているかではなく、その人の経験やスキルで給料が決まる
この仕組みは、会社がどんどん成長していた時代にはうまく機能していましたが、その一方で「どの大学を出たか」などの学歴で評価される傾向も強まっていきました。
学歴=能力と見なされた時代|企業が教育に与えた影響とは
企業が「優秀な人材」を選ぶとき、学歴がそのまま“能力の証明”とされるようになりました。その結果、教育の現場では次のような傾向が強まりました。
- 偏差値(学力の数字)で生徒を順位づけ
- 普通科高校(大学進学向け)が優先される
- 実践的な職業教育は価値が低いとみなされる
- 「いい大学に入れば、いい会社に就職できる」という社会通念の広がり
このような流れの中で、「将来の仕事に必要な力を育てる教育」は徐々に後回しにされていったのです。
不景気と大学進学率の上昇|“とりあえず進学”が招いた問題
1990年代にバブル経済が崩壊し、日本は長い不景気に突入します。企業の採用人数が減る中、若者の間では「就職できないなら、とりあえず進学しよう」という考え方が強まっていきました。
- 就職が難しい → 安定を求めて大学へ
- 大学に行く人が増える → 高卒で働く人が減る
- 「誰でも大学に入れる時代」になり、大学の質も問われるように
大学進学率の上昇は、単なる学びの意欲というよりも、働けない不安からの逃避であるケースも多かったのです。
職業教育が機能しない理由|学歴偏重社会が招いたミスマッチ
学歴を重視する社会の中で、現場で必要なスキルや仕事に直結する教育は見落とされてきました。その結果、以下のようなズレが起こります。
- 高学歴でも就ける仕事がない → 本来とは違う仕事に就くケースも
- 高卒でも力がある人が活躍できない環境
- 肉体労働や現場仕事(いわゆるブルーカラー)の人手不足が深刻に
仕事と学歴の対応関係が崩れたことで、人材のミスマッチが広がり、社会全体の効率も下がってしまっているのが現状です。
仕事に直結する教育とは?ジョブ型雇用とキャリア教育の必要性
2000年代以降、若者の就職難や非正規雇用の増加を背景に、「キャリア教育(将来の働き方を考える教育)」が注目されるようになりました。
さらに近年では、“何ができるか”で採用する「ジョブ型雇用」という考え方も広がりつつあります。これは、
- やる仕事を明確に決めて、それに合う人を雇う方式
- 大学名ではなく「実際に何ができるか」で評価
- 社会の求めるスキルを育てる教育が不可欠になる
というものです。
ただし、日本ではまだ「学歴で判断される」傾向が根強く、教育の側がこうした新しい働き方に十分対応できていないという課題があります。
日本の教育と雇用のズレを修正するには?職業教育再構築への道
これまでの日本では、以下のような流れが続いてきました.
- 経済成長 → 長く働ける会社中心の雇用制度(日本的雇用)
- 安定した雇用 → 学歴で人を選ぶ傾向が強まる
- 学歴社会 → 実践的な教育が軽視される
- 不景気 → 大学進学者が急増(働かないための進学)
- 教育と現実の仕事のズレ → 職業教育の存在感が薄れる
これからの社会では、「いい大学」ではなく「できること」「役に立つスキル」が問われる時代がやってきます。教育も、働き方の変化に対応した形へと変わっていくことが求められています。