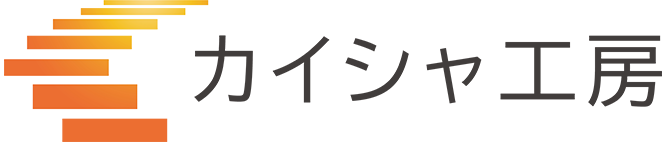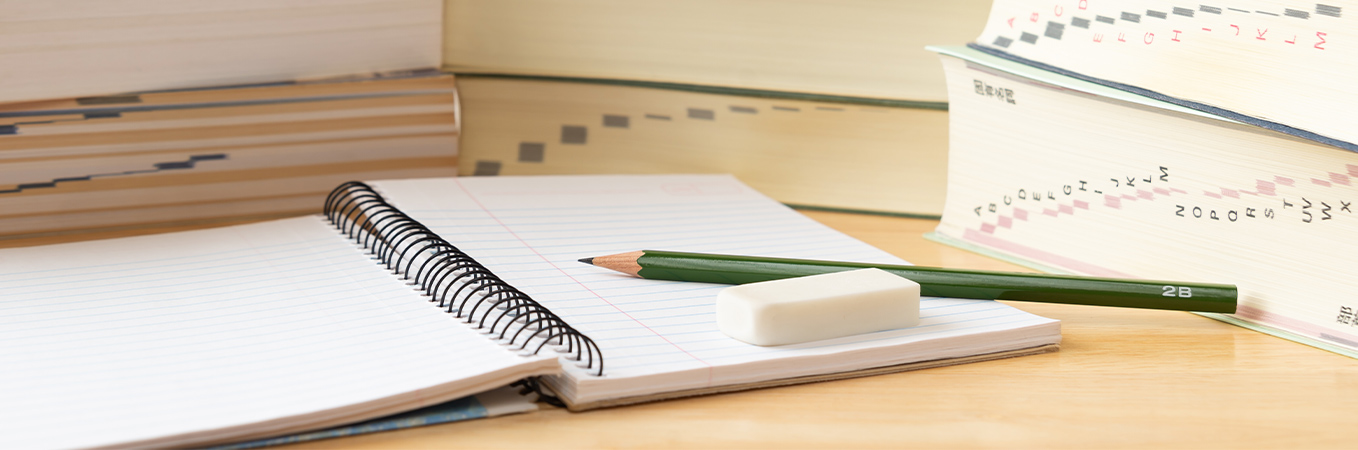教育格差という言葉を耳にしたことがあるだろうか。この言葉は、日本において比較的最近広まった概念であり、特に2000年代半ばから注目されるようになった。興味深いのは、英語には「格差」という単語が存在せず、「inequality(不平等)」として表現される点である。この違いからも、日本独自の視点が反映されていることが分かります。
本記事では、教育における格差と不平等について考え、その影響や背景を探っていきましょう。
教育にかかる費用と進学のハードル
2019年の調査によると、すべて公立の小学校・中学校・高校を卒業し、大学に進学するまでに必要な教育費(学校外教育費も含む)は、平均で約500万円とされている。この金額には塾や習い事、給食費、修学旅行費などが含まれます。
特に中学・高校に進学すると、塾の費用が増える傾向にあり、高校生になるとさらに支出が増大します。教育にかかるコストが家庭の経済状況に大きく依存することが、このデータからも読み取れるでしょう。
日本における子どもの貧困率
日本の子どもの貧困率は7人に1人とされています。これは、クラスに30人いるとすると、約4人が貧困状態にある計算になります。
貧困には「絶対的貧困」と「相対的貧困」があります。絶対的貧困とは、1日あたり1.9ドル(約300円)未満で生活する状態を指し、発展途上国で主に見られます。一方、日本を含む先進国では、「相対的貧困」という概念が用いられれ、手取り世帯所得が全国の中央値の半分以下の世帯を指し、日本では年間所得が127万円以下の場合が該当します。
この数値は、G7(先進7か国)の中でも特に高く、日本の社会課題の一つとなっている現象です。
教育の機会を均等にするための施策
教育の機会均等を目指して、日本ではさまざまな施策が行われてきました。その代表例が以下の制度です。
1. 義務教育費国庫負担法
1952年に制定されたこの法律により、教員の給与や学校設備の地域間格差の解消を目指しました。しかし、2000年代に入り、国庫負担の割合が3分の1に削減されたため、地域によっては再び格差が広がる可能性が指摘されています。
2. 高校無償化
2010年以降、高校の授業料が無償化される施策が進められました。しかし、所得制限があるため、すべての家庭に適用されるわけではありません。また、私立高校の支援範囲についても継続的な議論が行われています。
3. 奨学金制度
日本学生支援機構(旧・日本育英会)が提供する奨学金は、多くの学生にとって大学進学の支えとなっています。2020年には、就学支援新制度が開始され、給付型奨学金の拡充が行われました。
文化資本と社会関係資本が生む不平等
教育格差は、単なる経済的な問題だけではありません。「文化資本」と「社会関係資本」といった概念も、不平等の要因となり得ます。
文化資本とは?
文化資本とは、家庭環境や育ちの中で得られる知識や経験のことを指します。例えば、
- 本が多い家庭の子どもは学力が高い傾向にある。
- 美術や音楽に触れる機会が多い子どもは、知的好奇心が育まれる。
研究によると、日本では女性の方が文化資本を多く持つ傾向があるが、ジェンダーギャップ指数が低いこととどのように関連するのかは、さらなる研究が必要とされています。
社会関係資本とは?
社会関係資本とは、人とのつながりが生み出す価値のことで、いわば「人脈」のことを指します。
地域のつながりが強い場所では、学力が高い傾向があるとされています。一方で、助けを求めることができる関係がない人は、貧困に陥りやすいという研究結果もあります。
これからの教育のあり方
教育格差をなくすための議論は続いており、経済学者のアマルティア・センは「ケイパビリティ・アプローチ」という考え方を提唱しています。これは、
- 「実際にできること」だけでなく、「本来できるはずのこと」にも焦点を当てるべき。
- 教育によって選択肢を増やし、より良い人生を選べる社会を作るべき。
という考え方です。
日本では、新卒一括採用制度があるため、大学卒業後すぐに就職することが一般的です。しかし、世界的に見ると、大学進学のタイミングが遅かったり、国が学費を負担する代わりに卒業のハードルを高くする制度を採用している国もあります。
教育制度は、社会全体の仕組みと密接に関わっているため、どの方向に進むべきかについては慎重な議論が必要です。
まとめ
教育格差や不平等の問題は、一朝一夕で解決できるものではありません。しかし、
- 経済的な支援
- 文化資本・社会関係資本の充実
- 社会全体での教育に対する意識の向上
といった取り組みを通じて、より良い教育環境を実現することは可能です。
今後も、教育のあり方について考え、議論を深めていく必要があるでしょう。
もっと詳しく知りたい方へ
今回の内容は、Podcast番組をもとにまとめました。より詳しい対話形式での解説を聞きたい方は、ぜひPodcastをチェックしてみてください!